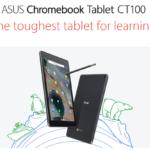
[かぶ] ASUS(US)がChromebookの新モデルC434とCT100の特設ページとプロモ動画を公開。
ASUSがCES2019で発表した新作Chromebook、C434とCT100がUSサイトで続々と特設ページ、プロモ動画等を公開しています。間もなくの発売を期待するとともに、国内での発表が楽しみでもあります。また3月30日にはASUS Store AkasakaにてChromebookのSESSIONも開催されます。今年のASUS JAPANの動向に期待(注目)です。
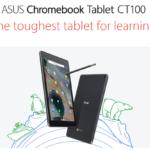
ASUSがCES2019で発表した新作Chromebook、C434とCT100がUSサイトで続々と特設ページ、プロモ動画等を公開しています。間もなくの発売を期待するとともに、国内での発表が楽しみでもあります。また3月30日にはASUS Store AkasakaにてChromebookのSESSIONも開催されます。今年のASUS JAPANの動向に期待(注目)です。
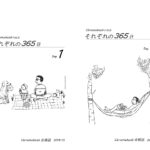
100人いれば100通りのChromebookとの付き合い方がある。それぞれの365日がある。いろいろな人の、いろいろな形の、いろいろな365日を眺めてみたい。そんな想いで昨年仲間を募り、12月に第1号を出すことが出来た、会報誌「Chromebook それぞれの365日」。今回第2号(Day 2)を発売することが出来ました。ご参加いただいた皆さん、前号をお読みいただいた皆さん、ありがとうございます。

Google Pixel Slateはキーボードが別売りとなっています。一般的にはGoogle純正のSlateキーボードを選ばれると思うのですが、もう一つ強力な選択肢があります。それが今回ご紹介するBRYDGEのG-Type Wireless keyboard for Google Pixel Slateです。本体と一体感のある厚みと質感、そして色。しっかりと固定されて反応もスムーズでキータッチも良好で、普段クラムシェルPCとしてどこでも気軽に開いて使いたい方にオススメのアクセサリーです。

「せっかく遠い日本からわざわざ来たのに、何故そこら中にある家電量販店に行きたいの?」米国で生まれ米国で育った16歳の従兄弟からすれば不思議だったのかもしれません。日本のChromebookユーザー「のごく一部」にとってはある意味ちょっと聖地みたいな場所でもあるお店、それがBest Buyです。Chromebook好きの私ですが、今回ようやく訪れることが出来ました。今回は気になったモデルと、実際に訪れてみての印象をご報告します。

今回、米国在住の従兄弟から学校の授業や自宅で使っているiPadの話を聞く中で、今まで私が感じてきたタブレット型のChrome OS端末(Chromebook Tab 10など)やDetachable端末(Pixel Slateなど)に対する違和感や疑問に対する答が少しずつではありますが見えてきたような「気がします」ので、この辺りで一度文章にしておきたいと思います。尚、一般的な明快な「このモデルは何?」といった答には一切答えていないことを予めお断りしておきます。

2019年2月下旬から3月頭にかけて、LAで暮らす叔父の家を訪問しておりました。叔父には現在16歳の息子がおり、現在El Segundo High Schoolに通っています。滞在中、学校の課題をiPadとG Suite+αを自然に活用しながら取り組んでいる従兄弟の姿を度々目にしました。そこで折角なので彼の学生生活におけるタブレットの活用について訊いてみました。

ASUS Storeの購入者特典が2019年3月2日から変更になります。Chromebookでは今まで全モデルに付いてきていた「延長保証パッケージトータル 2年」が税込5万円以上の製品のみとなるため、一部のモデルで影響が出てきます。特にASUS Storeのみの販売となるC223NAとC423NAはどちらも5万円未満のため、若干注意が必要です。ここ最近この2モデルの入手報告が続々と出てきていますので、改めてこれらのモデルの特長と魅力について考えてみたいと思います。

Google Pixel Slateはもちろん基本的な組み合わせ(本体とキーボードとペン)だけでも十分に快適に使えるデバイスです。ただ、お気に入りのラップトップPCにシールを貼ったりカスタマイズをする方がいるように、少し何かを加えることで、「より使いたくなる」デバイスになるかもしれません。長く愛用する上ではこうした感情(気分)がとても大切で効果的だからです。そこで今回は私が揃えたもの、これから揃えようと思っているものをご紹介します。

2018年11月末に発売されたGoogleの新しいChrome OS端末「Pixel Slate」。正直なところ、日々Pixelbookを愛用している私としては当初さほど真新しさもなく惹かれる部分もあまりなかったのも確かです。とはいえ「まったくの無視」はできない気になる何かがあったことも事実でした。そこで今回「実際に使ってみなければ何も分からない」と思い、最上位モデルの購入に至りました。まずは入手2日目の時点での印象です。

昨年海外では発表、発売されたものの、日本発売は未だ予定なく、また購入出来るモデルが限られていたことから、なかなか日本では話題にならなかったAcer Chromebook 514。ただ実際には気になっていた方も多いのではないかと思います。今回、米Amazonに待望のCPUにN3450を載せたモデルが入荷しました。そこで競合と考えられるASUS Chromebook C423NAの国内モデルと比較してみたいと思います。競合するようでいて意外と特徴が分かれる2モデルだと感じました。
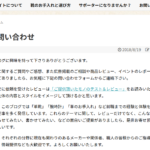
当ブログはChromebook特化サイトではありません。むしろ革靴やその他の内容でたまたまたどり着いた方も多くいらっしゃると思います。そういう方にとっては、日々発信しているChromebookの情報が理解できないだけでなく、不快に思われたり、内容によっては誤解を生んでしまう場合もあると思います。今回は頂いたメッセージの中から、日々こうした情報を発信する者として見落としがちな点について考えてみたいと思います。

昨年2018年末の米AmazonのBlack FridayとCyber MondayはChromebookユーザーにとっても大変に魅力的なセールでした。昨年発売されたばかりの話題のモデルだったSamsung Chromebook Plus V2とAcer Chromebook Spin 13がそれぞれ大幅な値下げをしていたからです。ところが今回、突然それらのモデルが昨年末とほぼ同じくらいの値下げが行われています。いつまで続くかはわかりませんが、複雑な気持ちではありますが、2つのモデルを改めて取り上げてみました。

ASUS JAPANが2019年2月6日、同社の公式オンラインストアであるASUS Store Online上にChromebookの特設ページを開設しました。今後情報はこちらに集約させつつ発信していくのだと思われます。各メーカー、それなりに自社サイトにChromebookのページは作成してはいますが、今回のように導入事例や役立つ情報も含めたまとまったページを作ったのは恐らく初なのではないか、と思っています。その影響と効果について考えてみたいと思います。

昨年2018年はChromebook各メーカーからハイスペックのモデルが続々と発表されましたが、その中の最上位モデルについてはなかなか実際に入荷はされずにいました。そうした中、今月に入り、続々と各社のモデルが展開され始めています。それぞれのモデルについて振り返りながら、入手方法も含めて振り返りたいと思います。

各社昨年発表したハイスペックChromebookの最上位モデルがようやく並び始めてきた時期ですが、そうした中、文章作成時点(2019年2月6日現在)、米Amazonにてセラー販売Amazon発送ながら最上位Core i7版のPixelbookが$454(28%)オフの$1,195.00になっています。既に発売から1年が経ちますが、昨年から今年にかけて私の最も愛用しているChromebookでもあり、今もその魅力は褪せないと思っています。

ひかりTVショッピングにおいて期間と台数限定でASUS Chromebookの名モデル、C100PAが「実質」9,800円となっています(29,800円で、クーポン適用でぷららポイント20,000pt還元)。思わず手を出したくなる「価格」ではありますが、もし「安いし、はじめてのChromebookとして良いかも」と考えて購入を検討されているのであれば、少しだけ考えて欲しいと思っています。その理由と現状について改めて文章にしました。

2020年に向けて国内でもそれぞれの教育現場に「何を」導入するか、といった話題が少しずつ盛んになってきています。それぞれの端末やOSに慣れ親しんでいる方にとっては一家言お持ちではないか、と思うのですが、ここで改めて「学校でのPC教育」というものについて考えてみたいと思います。それは単純に1日1時間とか週2〜3時間の授業だけのことなのでしょうか。今回はChromebookユーザーとして、教育現場に導入する際のChromebookのメリットについて、付随するサービスであるG Suiteと合わせて書いてみました。それは「Chromebookや特定の端末、OSに縛られない」ということだと思っています。

Chromebookの大きな魅力の一つとして「ウィルス対策が不要」という点が挙げられます。実際に非常にリスクも低くなっていて、そうした点も今回ネット上で話題になった「子供や高齢者にパソコンを与えるならChromebook」の理由の一つになっていると思っています。ただ、実際のところはどうなのでしょうか。今回は1年半前に私の身に起きた「日本人男性がお好きなロシアのお姉さん事件」と先日実家の父からきた「セキュリティシステムの破損」疑惑を中心に改めて考えてみたいと思います。

昨年末にお知らせしたGoogle+終了に伴うコミュニティの移行先ですが、当初の予定通りSlackでいくことにしました。昨年末からテスト運用をしてきましたが、現在考えられる中では運用面、また参加のしやすさ等を考えるとSlackが良いのではないか、との判断からです。既にGoogle+上では参加者の募集を始めましたが、ブログ上でもお知らせしたいと思います。Google+に参加されていた方(363人)も、また参加を躊躇っていた方も、多くの方に参加して頂けたら嬉しいなと思っています。